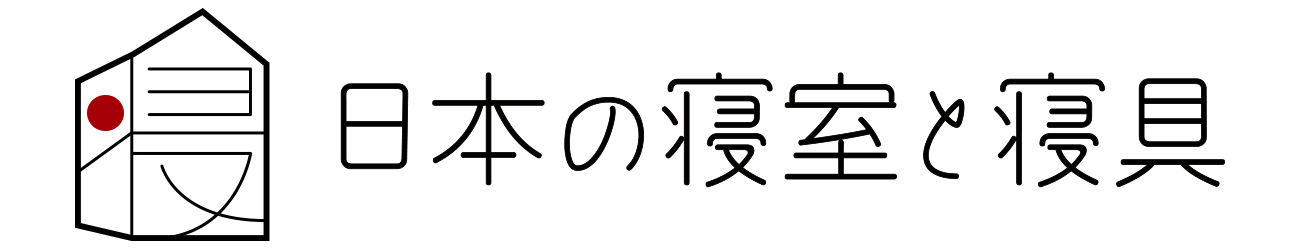専門家に聞く”ヒトと動物の眠り”【快眠コラム】
2025年3月26日
神川 康子

移動と変化の季節
エムール睡眠・生活研究所の所長で富山大学名誉教授の神川と申します。
日本の文化では、3月は人々の大移動の季節です。卒業、入学、入社、部署異動、転勤等々、別れと新しい出会いの季節でもあります。気温の乱高下もあれば、花粉症や黄砂も飛んできて、体調不良にもなりやすく、精神状態の乱高下も起こりがちですね。寂しい、悲しい、不安な気持ちもある一方で、満開の桜を心待ちにしながら新生活への期待も膨らみます。
少々残念な話ですが、なぜか離婚件数も3月が最も多くなるというデータがありますが、環境の変化やや心身のバランスが不安定になりがちだったり、もしかすると心機一転決断しやすい季節でもあるのかもしれません。
ヒトの環境適応力
人は多くの動物たちと違って、知恵(創り出す脳)によって環境に適応する力を身に付け、極寒の地や熱帯、海底や8,000mを超える山、宇宙空間でも生命を維持することが出来るようになってきました。しかし、それは何十万年もの月日をかけた科学の粋を集結した適応力であり、日々の暮らしの急な変動にそう簡単に適応しにくいのは、誰にとっても同じです。新生活や新環境に身を置いたら焦らず、楽しく人や環境をモニタリングしながら、徐々に慣れていきましょう。
ヒトの眠り、動物の眠り
どんなに歴史を積み重ねても、科学技術が進化しても変えられないのは、「ヒト」としての動物の部分です。
典型例は、どんなに努力してもヒトは、フクロウやコウモリのように夜行性にはなれないので、仕事やゲーム、趣味などで無理やり夜行性の行動を続けることはリスクを伴うことになりやすいのです。
つまり、環境や空間は暮らしやすいように工夫できても、時間まではなかなか操作できないのです。
反対に、多くの動物は人間のように知恵と科学でどのような場所でも生活する工夫が難しいので、気候条件や自然条件などに合わせて季節移動することになります。
白鳥が北へ渡り、ツバメが温かい所へ移動し、ヌーが餌となる草を求めて群れで移動する光景はテレビなどで見たことがあるでしょう。
活動しながら眠る、半球睡眠
このように命を守りながら移動や生活をするために「半球睡眠」と言って、脳の片方が眠っている間にもう片方が活動できる能力を獲得した動物たちがいます。
イルカやクジラは哺乳類で水中生活でも溺れないために。渡り鳥は群れで何千キロも飛び続けるので、仲間からはぐれないために。
この話を小学校ですると子ども達は「いいなぁ、授業ごとに脳の半分ずつ眠れたらいいのに!」と右目、左目を交互につむって練習しようとします。「どんなに頑張っても人間には無理ですよ!」と子どもの夢を破ってしまいます(笑)。
動物は自分や仲間の命を守るために、常に周囲の安全を確認したり、長距離の移動をしなくてはならないので、そのような眠り方を進化の過程で獲得してきました。子ども達には学校で居眠りしても渡り鳥のように群れから外れて迷子になることは無いのですが、勉強の迷子になりますよ!と笑いながら説明します。
ナマケモノは本当にナマケモノ?
動物の世界では、身体が大きくても草食系で肉食の動物に襲われがちなゾウや馬などは長時間眠らなかったり、弱い動物でも他の動物に襲われにく高い木の上で眠るコアラやナマケモノのような動物はとても長く眠れたり、木の葉を少量しか食べない動物がエネルギーを使い果たさないように長時間眠ったり、ユーカリのような餌に含まれる毒素を分解するために長く眠ったりと、それぞれ理に叶った眠り方を進化の過程で獲得してきたのです。
ところが、日本では15~18時間眠る動物に「ナマケモノ」という名前を付けています。英語では「sloth スロース」と言います。行動がゆっくりしている特徴で命名されたようです。ちなみにフランス語では「reve レーヴ」で「夢」という意味の呼び名だそうです。どんな動物も健康に生きるための眠り方を獲得してきているのに「ナマケモノ」とは、ちょっと申し訳ない気もしませんか?
人間に合った健康を維持するための眠り方
人間にも脳が進化した動物として、心身の健康を維持するための眠り方があるので、変化に富む3月だからこそ、こころやからだのバランスを崩さないように、心地よい眠りを追究して、健康な生活を維持しましょう。
地球上の全ての生命は休んだらエネルギーチャージができて、また元気に活動できます。興味のある方は色々な動物の眠りを調べてみてはいかがでしょうか?
ちなみに、私たちが開発した「すいみん・かるた」の45枚の絵札には全部異なる動物が描かれているので、ぜひ参考にしてみて下さい。
すいみん・かるた
家族や職場で睡眠を改善したい方のために「すいみん・かるた」(dreams come true=良い眠りは人生の夢を実現する)を作成しています。お子様との学びの場でぜひご活用ください。大人にとっても学びのある内容になっています。
今日から実践できる睡眠改善方法
睡眠教育を実施してみようという教育者の方、保護者の皆様、企業内の人事や健康管理を担当されている方、ぜひ下記のURLから「睡眠を改善する生活習慣15項目」に答えてみて参考にしてください。
昨年までの睡眠研究で、この15項目から3つを選んで2週間チャレンジして下さると、61%の方で睡眠が改善したという結果になりました。残りの39%に入りそうな方はもうあと2項目を加えてみて下さい。
.
睡眠環境と習慣を学びたい方におすすめ
【PR】睡眠環境と睡眠習慣を体系的に学びたい方、知識はあってもなかなか実践できないという方には、エムール睡眠・生活研究所(所長:神川康子)と通信教育のユーキャンが共同開発した『睡眠セルフマネジメント講座』がおすすめです。テキストで睡眠のしくみや、睡眠の質を高める実践法などの知識を身につけながら、副教材やアプリで睡眠のくせを見える化!2つの学習を進めていくことで資格取得と快眠習慣の定着、両方を目指せます。
.
いずれもリンクフリーです。ぜひ睡眠教育の実践にお役立ていただければと存じます。