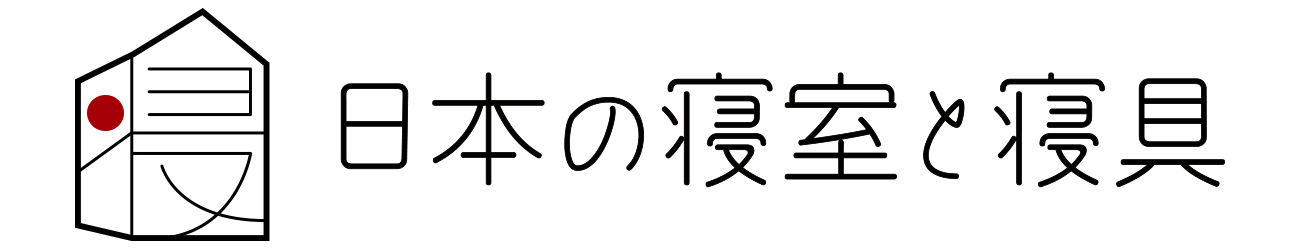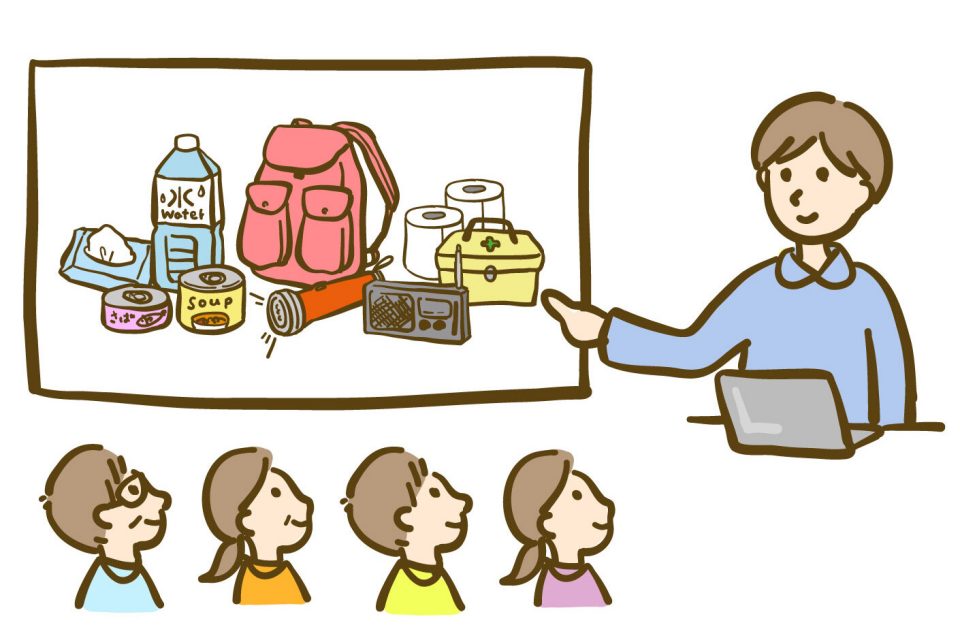【快眠コラム】避難所での睡眠環境
2024年2月28日
神川 康子

災害時は一瞬で日常が奪われる
これまでの多くの講演で、子ども達の心身の成長や学力の向上のために、そして100年人生時代においてこそ、人々が健康を維持向上していくためには毎日の「睡眠」が「栄養」と同じくらい重要な鍵を握るという解説をしてきました。
その際に安定した睡眠が得られない究極的な環境として「戦争」「飢餓」「家が無い」の3条件を挙げてきました。
世界に目を転じても、今の日本国内を見ても、まったく他人ごとではありません。
まさに頻繁に起こる災害時には、一瞬にして「安心・安眠できる家」が奪われてしまいます。
災害時の睡眠
災害時の睡眠についての水野らの研究(基礎講座睡眠改善学70-73頁)によると、避難所では余震などの不安や騒音、明るさ、高温・低温環境、床の硬さ、人の動き、埃などによる咳き込み等々の要因で睡眠効率(横になっている時間のうち眠れている時間の割合)が(40%程度まで)著しく下がることが分っています。
東日本大震災の際に偶然睡眠測定された高齢者でも震災の後に自宅に戻れた際には睡眠効率が回復することも確認されていますが、今回の能登半島地震では全壊や半壊、火災で戻る家自体が無くなってしまった方々が3万人以上いらっしゃいました。
眠る環境のために備えておく
1日でも早く良い睡眠を取って頂き、不安や疲労、体調不良や持病悪化からも解放されますようにと願うばかりです。
避難場所では段ボールベッドだけでなく、寝袋や寝具、保温性の高い衣類、とくに下半身を冷えから守れるような衣類や毛布などを十分に確保することが、冬季には命を守るために優先的に配慮していきたいことです。
さらに体温調節機能が十分でない乳幼児や高齢者にはいっそうの注意を払っていくことが大切です。
騒音や明るさのコントロールについても避難所の規模が大きくなるほど、困難になり、眠るために確保したい30dB(図書館位の静かさ)以下や、30Lx(豆電球位の明るさ)以下にすることが困難になり、眠れない人々も多くなります。
迅速に暮らしを整える災害対策
日頃は何気なく確保できている自分好みの睡眠環境が災害時には確保しにくくなる事から、災害時にも眠れる環境の確保は、災害関連死を予防するためにも1.5次避難、2次避難前の避難所生活から想定の上に迅速に保証できるような災害対策が急務です。
災害が起こるたびに少しずつは進化しますが、ライフラインの確保、飲食、トイレ、入浴、安眠環境の確保を、個人でも行政でも喫緊の課題にしなければならない、年間を通してどこでも予断を許さない災害の多い日本の現状となっています。
頑張りすぎず眠りを優先しよう
元旦の能登半島地震から2か月近く経ち、精神疲労が遅れてやってくるような気がしています。
私自身も当初2週間ほどは片付けや余震の不安などからあまりよく眠れなかったのですが、ストレスや疲労は自覚しないうちに一定量蓄積してから現れるのか、最近は睡眠効率が90%を超えることも多くなっています。
疲労やストレスも最初は緊張感から交感神経優位になり睡眠の質量が悪化するのですが、過度に蓄積すると人体の防衛本能によって心身を休める睡眠が優先されることも分かっています。
このような時ほど本能に従って眠りを優先しましょう。
無理をして眠らないで頑張りすぎると、過労死や労災認定時に議論されるように、次第に心(精神)にダメージが及び、日常生活やときに生死を分ける人生の判断力すら失われてしまう可能性もあります。
私の場合は単に日頃のデスクワークよりも後片付けなどで身体を良く動かしたことによる睡眠効率の上昇だったのかもしれません。
災害避難時にはしっかり身体を動かすことも、エコノミークラス症候群などと呼ばれる循環器系の病気(静脈血栓塞栓症など)を避けるためにも重要なので、周囲の人たちと体操をするなどの活動も促し合いましょう。
子ども達が高齢者を促して一緒に運動している光景は、みんなも元気に笑顔にしてくれます。
身体を動かすための動画紹介
エムールでも、J1リーグ所属クラブ『東京ヴェルディ』監修のフレイル予防体操の動画コンテンツをこちらで公開しています。
また、富山県教育委員会でも「親子で楽しめる運動遊び」などの動画も配信しています。参考にして頂けましたら幸いです。
アンケートご協力のお願い
本記事の著者であり、エムールの睡眠・生活研究所の所長でもある神川康子から、アンケートのご協力のお願いです。
できるだけ多くの方々から広くデータを集め、睡眠の質を高めるための生活習慣の取り組みをどのくらいなされているのかを調査しています。
3分程度で完了する簡単なアンケートになっており、結果はこちらのメディアでも開示予定です。
よろしければご協力をお願いいたします。
.