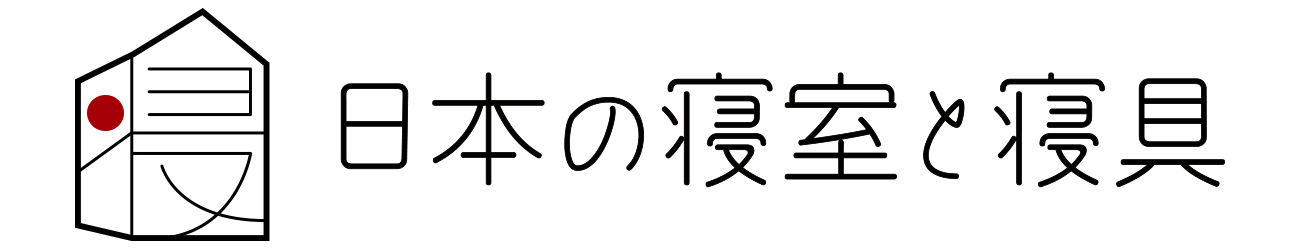専門家に聞く”子どもの脳の発達のための睡眠”【快眠コラム】
2025年4月25日
神川 康子
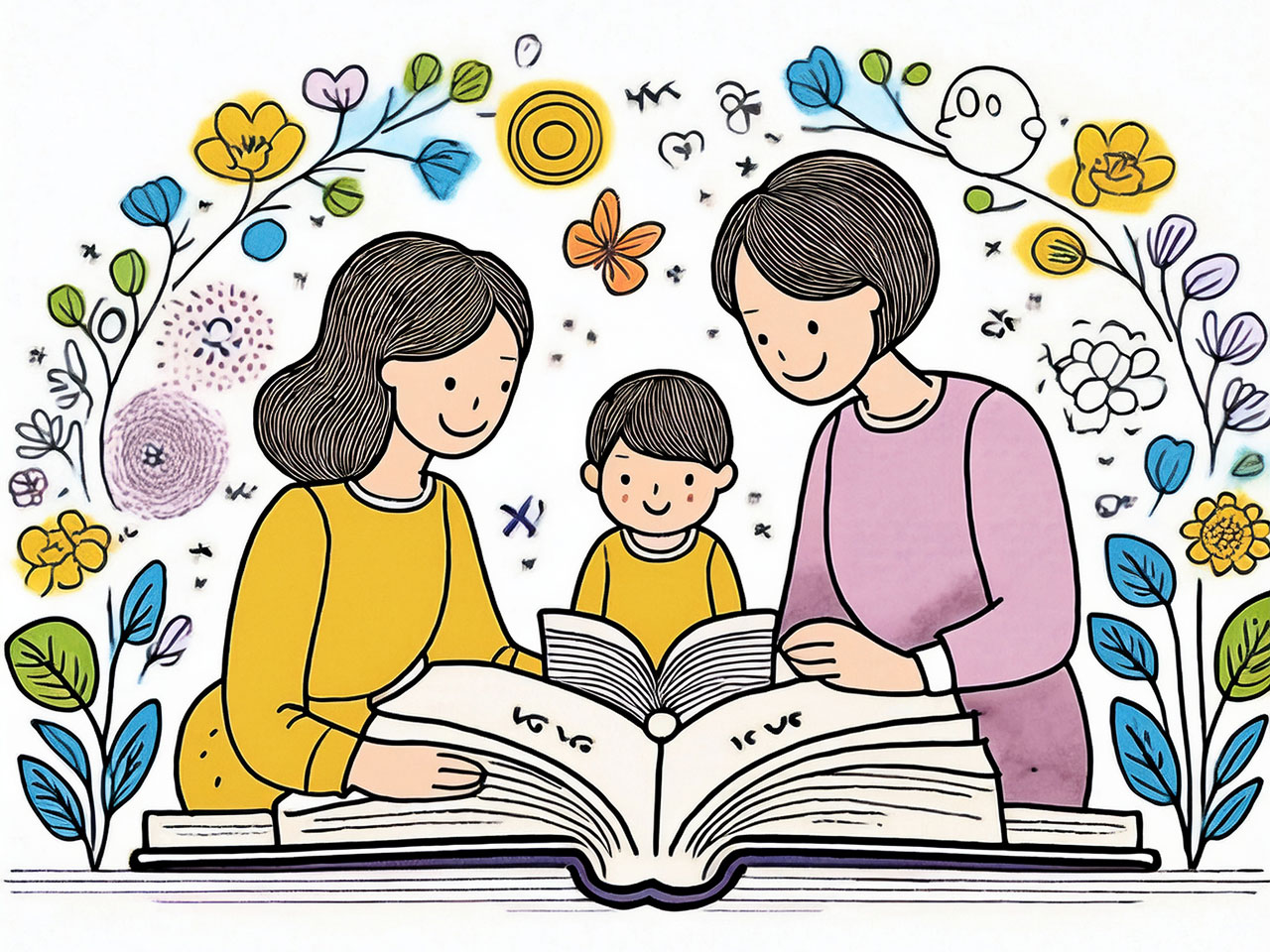
目次
子供の健やかな成長のために
エムール睡眠・生活研究所の所長で富山大学名誉教授の神川と申します。
大谷翔平選手のご家族に女のお子さんが誕生して、とても嬉しいニュースとなっています。大谷翔平選手ご自身が睡眠を大切にすることでも有名ですので、お子様の睡眠も大切になさるのではないかと想像しています。
どこのご家庭でも楽しみにしていたお子さんの誕生によって、とにかく元気に育ってほしいと願う日々の中で、病気や怪我はしないでほしいと、新しい心配や不安が生じてくるのは、みな同じですね。
そして子どもが成長するにしたがって「這えば立て、立てば歩めの親心」と、親の願いはどんどん膨らんでいき、際限がないかもしれません。
子どもの成長と睡眠・生活習慣や環境について研究する私たちは、子どもが健やかに育つために周りの大人ができる事を考え続けています。そこで、今回は「子どもの脳の発達と睡眠」についてお話いたします。
脳の成長・発達の順番
まず、子どもの成長にとって、生まれてすぐに支えたいことは脳の発達です。脳はこれからの長い人生を生き抜いていくために必要な身体活動や知識や生活技術などを吸収し、考えたり判断したりする心も成長・発達させていくためのベースであり、コントローラーとなっていく器官だからです。
からだ脳”の成長
脳の成長・発達には順番があり、脳という器(うつわ)がしっかりしていないところに、英才教育のように大人が望む多くのものは詰め込めないという事です。最初は「寝る」「食べる」「身体を動かす」という命に係わる“からだ脳(脳幹や大脳辺縁系)”が育ちます。この乳幼児期の一番大切な生活行動は、「しっかり眠る」、「活発に身体を動かし、おもいきり遊ぶ」、「楽しく積極的に食べる(授乳や哺乳も)」、そして「五感を使って感情(喜怒哀楽など)を共有できる周囲とのコミュニケーションや体験」なのです。
“かしこい脳”と”こころ脳”の成長
“からだ脳”が成長しはじめると“かしこい脳(大脳新皮質)”も1歳ころから育ち始め、言語や知識を蓄え、運動能力も向上して、社会性なども成人するまで発達していきます。
さらに人間として大切な“こころ脳(前頭葉)”とも言われる考えたり判断したり、感情をコントロールしたり、倫理的な思考をする脳は10歳頃からめざましく成長して行きます。
3歳までは詰め込み勉強よりも多様な体験
大人の願いが先走って、赤ちゃんの時から勉強などの詰め込み教育を行っても天才や秀才になる事は期待しにくく、実際は、五感や全身を使った多様な体験を通して、3歳頃がピークとされる神経細胞どうしの繋がり(シナプス:神経回路)を増やしておいたほうが、その後の教育期間に学習効果を上げ続けていくためには有効であることも分かっています。
シナプスの剪定
日々の日常生活から受ける多様な刺激によって、一度増えたシナプス(神経回路)は淘汰され、神経伝達物質をより多く、より速く放出できるシナプスが残るという経過をたどります。そうして得意なこと、好きなこと、繰り返し行っていることがいっそう上達し、脳はもちろんのこと、身体とこころが成長し、知識や技術をさらに吸収して、多様な人々との関りから他者理解が深まり、人間力も向上して行くことになります。
子供の成長に合わせた大人の役割
大人が手助けし支える環境の中で子ども達にしっかりした脳という器を作り、次第に子ども自身が自分で考え自立して行けるようにサポートすることが理想的です。「はじめはしっかり手をかけて“からだ脳”を育て、やがて自分でできる事が増えてきたら目をかけ(見守り)、やがて思春期を過ぎてきたころからは信頼して、心をかける」というように“かしこい脳”と“こころ脳”が成長してほしいと願っています。
睡眠は脳の栄養源
子どもにとって「睡眠」は胎児からの発達段階の全過程において、へその緒や口から得られる栄養以上に「脳の栄養源」となり、脳の発達のベース基地となることを大人がもっと理解してほしいと、日々睡眠教育を続けています。
そして子どもが自分で考えて生活環境の整備ができるようになる(自己管理能力がつく)までは、安心し、リラックスして深い眠りが十分にとれる家庭環境、地域環境、社会環境を大人から意識して頂きたいと願います。
脳と睡眠はともだち
まだまだ「眠りを削って頑張り続けようとする」日本人が多い状況をなんとか改善したいと研究を進めています。「脳」と「睡眠」はともだち(良い関係)で、子ども達の「脳」が元気に成長してくれるように、現在「脳とすいみんはともだち」という、ゲームをしながら元気な脳になってもらえるボードゲームを作成中です。乞うご期待!
今日から実践できる睡眠改善方法
睡眠教育を実施してみようという教育者の方、保護者の皆様、企業内の人事や健康管理を担当されている方、ぜひ下記のURLから「睡眠を改善する生活習慣15項目」に答えてみて参考にしてください。
昨年までの睡眠研究で、この15項目から3つを選んで2週間チャレンジして下さると、61%の方で睡眠が改善したという結果になりました。残りの39%に入りそうな方はもうあと2項目を加えてみて下さい。
.
すいみん・かるた
家族や職場で睡眠を改善したい方のために「すいみん・かるた」(dreams come true=良い眠りは人生の夢を実現する)を作成しました。お子様との学びの場でぜひご活用ください。大人にとっても学びのある内容になっています。
睡眠環境と習慣を学びたい方におすすめ
【PR】睡眠環境と睡眠習慣を体系的に学びたい方、知識はあってもなかなか実践できないという方には、エムール睡眠・生活研究所(所長:神川康子)と通信教育のユーキャンが共同開発した『睡眠セルフマネジメント講座』がおすすめです。テキストで睡眠のしくみや、睡眠の質を高める実践法などの知識を身につけながら、副教材やアプリで睡眠のくせを見える化!2つの学習を進めていくことで資格取得と快眠習慣の定着、両方を目指せます。
.
いずれもリンクフリーです。ぜひ睡眠教育の実践にお役立ていただければと存じます。